
先日
読売テレビにて人気シリーズの
吹奏楽の旅
が放送されました。
ずっとシリーズ化されたこの
吹奏楽部をドキュメントしたコーナーは、いろんな学校が取り上げられ、
名物先生と名物生徒とのいろんなやり取りが
生き生きと描かれていました。
今回は、20年前に放送された
淀川工業高等学校吹奏楽部の
丸谷明夫先生と吹奏楽部の生徒たちのドキュメントを
現在の部員たちと、ゲストの方々と一緒に観るという企画でした。
6年前の春まで、私の息子がこの学校、この部活に所属していました。
だからこの番組に
今、この時に淀工吹奏楽部が取り上げられることは
複雑でありうれしく寂しい機会となりました。

ゲストには、世界的大指揮者 佐渡裕さんや、アーティスティックスイミングの、名物コーチの井村雅代さんも出演されていました。
お二人は、生前の丸谷先生と同士として深く親交されておられました。
今の淀工吹奏楽部の学生は、3年生も丸谷先生の生の指導を受けたことがありません。
伝統としては、日本一の吹奏楽部に所属していても
丸谷先生がいなくなった部活は、
社会的に練習における規制が増えたこともあって全く違うものになっています。
だから、仕方がないのですが、音も違うように聞こえます
それが証拠に
丸谷先生のおられたころの淀工は、毎年行われる3つの全国コンクールには当然のごとく出場し
毎年金賞を取るようになっていて、通算金賞回数は、32回ダントツに日本一だったのですが、
丸谷先生がおられなくなってからの淀工は、
一年目は出場辞退し、次の年は、全国に出たものの銀賞
そして、次からは、関西大会までで次にいけないことが続いています。
毎年、メンバーが変わる部活では、その年のメンバーによってできは左右するはずですが、
毎年必ず、全国大会で金賞が取れるだけのクオリティにまで引き上げていく丸谷先生の手腕は、
誰も真似ができないものだということを証明したようなものですが、
淀工吹奏楽部というブランドは、50年続いてきたので、
それを現役の部員にも知ってほしいとたぶん、
OBが番組に企画を申し出たのではないかと勝手に想像しています。
番組の中では、
20年前のその当時のコンクール前の様子がずっと時系列で追いかけて取材されていましたが、
実際に息子が体験したあの頃を思い出して、
いろんなことがありましたし、本当に苦しく大変な二年間だったと思い出しました。
1年生は、神様のように扱ってもらえて、楽しく朗らかに幸せな一年を過ごしましたが、2年目からはまさに
自分との闘い
と、
淀工という看板を背負う重圧と戦う日々
先生の求められる高見が全然わからなくて苦しむ毎日だったと思います。
思い出されるのは、
全国コンクール1か月ほど前
夜12時近くに帰ってくる息子が、悶々としている様子で、明らかにしんどそうで、
もちろん体力的にもしんどくて
大丈夫かなぁと思っていました。
何に悩んでいるのか尋ねてみると、
先生は、
何かが違うんや
とおっしゃっていたそうです。
確かに音を聞くと例年のサウンドと何かが違うのです。
それを一人一人考えろという宿題に、子どもたちは毎日悶々と立ち向かっていました。
最後全国コンクールの直前の壮行会で演奏を聴いたとき
私は、涙をこらえることができずに号泣してしまって普通の感情ではいられなくなっていました。
なぜなら、
この年の全国コンクールという目線で見たとすると、金賞は確実に取れるだろうというサウンドに仕上がっていたのですが、
先生の指揮からは、
もっとお前らできるやろ?
というような覇気を感じたからです。
高校生のレベルなんてものを見ているんじゃない
もっともっと今の音からさらに良い音を目指して、
音楽の奥の奥には、もっとほら、こんなこともこんなことも転がっているやろ?
それを感じて、もっと表現して、もっと楽しんで、
と言ってくださっているような
そんなことが丸谷先生の背中から伝わってきて、
正直
丸谷先生、今年で引退されるんじゃないか?と思ったほどの気迫だったのです。
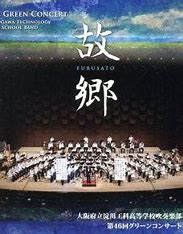
コンクール当日の演奏は、先生自身も緊張されていて
また子どもたちも、緊張していて、
いつもの絶好調の時の演奏はできなかったようですが、
賞としては、もちろん金賞
そして、のちに、コンクールでのいろんな学校の名演を集めたCDに
この年次の演奏は、たった1校
課題曲自由曲連続で、演奏会の雰囲気そのままに収録されていたほどの名演と評価されました。
それでも、子どもたちも頑張っている途中のような気持ちで本番を終えたのでした。
自分で高見の頂点に至ることができたという実感ではなく、
音楽というものが青天井だということを体感することができての終焉だったのです。
音楽をずっとやってきた私でも、そんな経験はしたことがなく、
発表会でまあまあ弾けたら御の字
コンクールでも、努力賞が取れても万々歳
その程度しか、経験したことはありませんが、
あの時の息子をそばで応援できた経験は、指導者としても親としても宝物です。
番組の最後に、青山学院大学の陸上部の監督が、コメントを言っておられました。
今の教育の現場では、楽しいことを求めることが主流ですが
丸谷先生は、生徒と一緒に、一つのものを作り上げる同志として真剣勝負をしていたんだと思う。
何かを目指して、限界まで頑張ってこそ見えること、
また、そこで、負けたとしても悔しいと思うことで、人間力が高まるとも。

まさにそうだと思いました。
上っ面の楽しさだけを目指していたのでは、
絶対たどり着けない高見
それを目指して、届かなかったときにもまた、
人間力、人としての奥行きが育つ
それを、私は、息子を通じて、
丸谷先生に見せていただけたという自負があります。
教育とは、
子どもだけではたどり着けない可能性を、
信じる大人、指導者がいることが、
とても大事だと信じて、
これからも子どもたちと対峙していきたいと思います。
丸谷先生は、本当に素晴らしいし、
丸谷先生の紡いでこられた音は、
音を聞くだけでわかるくらい、丸谷先生に心酔していた私は、
番組を見ながらも何度も涙があふれてきましたが、
おかげさまで、子どもたちを磨く仕事をさせてもらえているので、
丸谷先生の思いを胸に、
子ども達を磨いていきたいと思います。